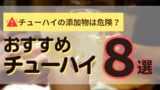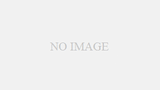友達同士の飲み会の場で飲むお酒や気分転換にひとりで嗜むお酒など、お酒の飲み方は人それぞれでしょう。
どうせ飲むなら気分良く飲みたいところですが、ここで気になるのが、アルコール度数や糖質・プリン体といったお酒を選ぶ上での指標はもちろん、何よりも健康への影響ではないでしょうか。
本記事では、体に悪いお酒の特徴や種類をランキング形式で紹介、そして体に負担のない飲み方などをわかりやすく解説します。
体に悪いお酒の特徴、基準
一般的にお酒が体に悪いといった解釈は、お酒に含まれるアルコール度数や糖質の割合が高くなることに起因するとされていますが、そんな体に悪いお酒について、どのような特徴や基準があるのかを解説します。
アルコール度数が高い
アルコール度数が高いお酒は、肝臓への負担が大きくなりがちです。
例え飲酒量が少量であっても、アルコール度数が高いお酒は、アルコール度数の少ないお酒を同量飲む場合に比べると、肝臓での分解過程で体に余分な負担がかかってしまうからです。
糖質が多い
ビールや発泡酒に代表されるお酒には、糖質が多く含まれています。
糖質が多いと、体に次のような悪影響を及ぼします。
- 糖質を摂りすぎると体脂肪として体に蓄積される→肥満の原因になる。
- 糖質を頻繁に摂ることで血糖値が上昇する→動脈硬化や糖尿病のリスクが増える。
- その他、体重増加や免疫力の低下につながる。
カロリーが多い
カロリーは、糖質と密接な関係にありますが、カロリー=糖質ではありません。
糖質は体の中でエネルギーを作るための材料で、カロリーはそのエネルギーの単位として捉えた方がわかりやすいでしょう。
市販のお酒には、国税庁による「表示義務がない」ことを理由にカロリー表示がありません。
しかしながら、カロリーが多いお酒は、飲みすぎると糖質同様、肥満の原因にもなるし血糖値の上昇により動脈硬化や糖尿病のリスクにつながります。
添加物の多さ
お酒に含まれる添加物としては酸味料、着色料、香料などがあります。
特に安価なお酒は、製造過程で省く工程により、本来の色や香り、甘みなどを人工的に添加するため、健康への悪影響をもたらすリスクがあり、体にも悪いといえます。
関連:チューハイの添加物は危険?おすすめの無添加チューハイは?
不純物の多さ
主に日本酒やビール・ワインなどで生じる「発酵」の製造工程で発生する不純物として考えられるものが、乳酸やコハク酸に代表される有機酸、そして酸味料や糖類などの添加物でしょう。
一方で、日本酒でも純米酒は、不純物などの影響が少ないとされているので、ここでも安価なお酒の方が不純物多いといえます。
純アルコール量の多さ
お酒に含まれるアルコールの量は、純アルコール量として表すことができ、飲酒の目安とされています。
純アルコール量は、一般的にアルコール度数x飲酒量x0.8(比重)で計算することができます。
具体的に見ると、例えばビール500mlでアルコール度数5%の場合、純アルコール量は20g、焼酎1号(180ml)35度の場合、純アルコール量は50gになります。
厚生労働省が定めるアルコールに関してのガイドラインによると、「適度な飲酒」の項目では、純アルコール量は一日約20g程度と記載されており、これを超える量は健康への悪影響をもたらすとしています。
体に悪いお酒の種類ランキング
この章では、体に悪いとされるお酒の種類ランキングTOP10として挙げられるお酒を種類別に説明します。
だだし、ここで挙げるお酒が無条件に体に悪いわけではなく、飲む量や頻度が多ければ体への負担リスクが増すということは覚えておきましょう。
- チューハイ
- 日本酒
- ビール
- 発泡酒
- 焼酎
- ウィスキー
- ワイン
- カクテル
- ブランデー
- 果実酒
1.チューハイ
ビールや焼酎よりも安価な酎ハイは、アルコール度数が3〜5度と比較的低く手軽に飲めるので、常に人気上位です。
そんな中、アルコール度数が7〜9度のストロング酎ハイは、飲みやすい割には酔いやすく、飲み過ぎには要注意です。
| アルコール度数 | 3〜5度 ストロング酎ハイは7〜9度 |
| 糖分(糖質) | 純粋な焼酎ベースのチューハイは低いが、果汁やジュースで割った酎ハイは糖分が多め |
| 添加物 | 酸味料、香料、着色料 |
| 不純物 | 人工甘味料など |
2.日本酒
日本酒は米を原料とする醸造酒で、糖分やアルコール度数が比較的高く、添加物も含まれているため、飲みすぎると肝臓への負担が多くなり、肥満や糖尿病などの健康被害リスクが高くなります。
日本酒はそこそこのお値段の「純米酒」であれば、体にアルコールも残りづらいのでおすすめです。
| アルコール度数 | 平均で約15〜16度 |
| 糖分(糖質) | 100mlあたり約2.5g |
| 添加物 | 醸造アルコール、糖類(甘み成分)、酸味料(乳酸、コハク、クエン酸、リンゴ酸)等 |
| 不純物 | オリ(白濁)、タンパク質等 |
*酒税法により、清酒のアルコール度数は22%以下と定められています。
3.ビール
麦芽・ホップ・酵母・水を主原料とするビールは、添加物などの副原料が入ることでコク・キレ・うまみなどの味を引き出しています。
ビールは糖質やプリン体が多く含まれるので、飲み過ぎると肝臓への負担や尿酸値の増加など健康リスクが増加します。
体のことを考えてビールを飲むなら「糖質ゼロ、プリン体ゼロ」のビールがキーワードになります
| アルコール度数 | おおよそ3.5〜5度 |
| 糖分(糖質) | ビール350mlあたり約10g |
| 添加物 | 麦芽、ホップ、コーン、糖類など |
| 不純物 | オリ(白濁)など |
4.発泡酒
発泡酒はビールと同じように麦芽やホップを原料としますが、発泡酒の場合、麦芽比率はビールの50%以上に対して50%未満と定義されています。
さらにビールとの比較でいうと、概ねビールよりも発泡酒の方が安くなっており、酒税法ではビールと発泡酒は、使用する原料および麦芽の使用割合によって区別されます。
発泡酒が体に与える影響について、ビールとの比較で見てみると、アルコール度数は低く、プリン体は少なめですが、カロリーや糖質については高めとなり、飲み過ぎには注意が必要です。
買う時は低カロリーを優先して探すのがおすすめです。
| アルコール度数 | おおよそ3〜6度 |
| 糖分(糖質) | 100gあたり3.6g |
| 添加物 | ホップ、麦芽エキス、糖類、酸味料、乳化剤、香料、カラメルエキスなど |
| 不純物 | オリ(白濁)など |
5.焼酎
蒸留酒である焼酎にはプリン体や糖質は含まれませんが、アルコール度数が比較的高いので、飲み過ぎによる高血糖リスクがあります。
| アルコール度数 | おおよそ20〜25度 |
| 糖分(糖質) | 糖質ゼロ |
| 添加物 | 麹と水以外の添加物なし(本格焼酎に限る) |
| 不純物 | 不純物オリ(白濁) |
6.ウイスキー
ウイスキーは、焼酎の製法と同じ蒸留酒で低カロリー、糖質・プリン体ゼロが特徴ですが、比較的アルコール度数が高く、飲み過ぎによる高血糖の症状には注意が必要です。
| アルコール度数 | おおよそ40〜43度 |
| 糖分(糖質) | 糖質ゼロ |
| 添加物 | 原料以外の添加物なし |
| 不純物 | 不純物オリ(白濁) |
7.ワイン
ワインは白ワインと赤ワインに大別され、特に赤ワインには健康に良いとされるポリフェノールの含有率が高いとされています。
しかしながら、市販のワインには酸化防止剤として亜硫酸塩が含まれていたり、アルコール度数が比較的低い分、飲み過ぎによる健康への悪影響が懸念されます。
| アルコール度数 | おおよそ12度 |
| 糖分(糖質) | 白ワイン:100ml当たり2.0g
赤ワイン:100ml当たり1.5g |
| 添加物 | 酸化防止剤(亜硫酸塩) |
| 不純物 | 酒石酸 |
8.カクテル
カクテルは比較的アルコール度数の高いリキュールはじめ、フルーツジュースやトマトジュースなどの塩分・糖分が含まれる材料が使われることが多いため、嗜む程度にした方が健康へのリスクが少なくなると考えた方がいいでしょう。
| アルコール度数 | 25パーセントが主流で、40度前後もある |
| 糖分(糖質) | 割り剤によるが、比較的糖質が高い |
| 添加物 | 着色料、保存料(安息香酸ナトリウム) |
| 不純物 | 氷に含まれる不純物がまれにある |
9.ブランデー
蒸留酒のブランデーは、糖質ゼロでポリフェノール効果があるので、殺菌作用や消化促進機能が期待できます。
しかしながら、アルコール度数が高いため、飲み過ぎによる健康へのリスクは高くなります。
| アルコール度数 | おおよそ37〜50度 |
| 糖分(糖質) | 糖質ゼロ |
| 添加物 | ブランデーエッセンス(香料製剤) |
| 不純物 | 不純物オリ(白濁) |
10.果実酒
梅酒をはじめ、レモン酒やいちじく酒など、代表的な果実酒は飲み方によっては、疲労回復や食欲増進などの効果があります。
でも梅酒などは糖分が高く、果実酒全般、アルコールが含まれているため、飲み過ぎによる健康リスクが伴います。
| アルコール度数 | おおよそ5〜15度 |
| 糖分(糖質) | 梅酒90mlあたり20.7g |
| 添加物 | 保存料など(酒税法による定めあり) |
| 不純物 | 不純物オリ(白濁) |
体に優しいお酒の飲み方
「お酒は百薬の長」とは、古くから言い伝えられてきたことばですが、これには「ほどほどに嗜む」ことが大切であるとされています。
この章では、そんなお酒の体への負担を考えた飲み方を解説します。
適量のお酒を飲む
お酒は、飲み過ぎることで脳の働きを低下させ、酩酊状態を招くことがあります。
これを防ぐためには、自分がどれくらい飲めば飲み過ぎになるかを知ることが必要になります。
適量のお酒を飲むための基準としては、ほろ酔い状態の次の段階になる前にセーブすることでしょう。
これを超えてしまうと、気が大きくなってしまい飲み過ぎへとつながります。
つまみを選ぶ
お酒に含まれるアルコールは、胃の粘膜に影響を及ぼし、悪酔いへと導いてしまうため、予め飲む前に牛乳やヨーグルトで保護しておく方法があります。
また、アルコール単体で飲むことを避け、食事やつまみと一緒に飲むこともおすすめです。
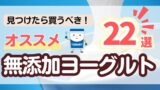
割って飲む
例えばアルコール度数の比較的高い焼酎やウイスキーは、炭酸や水で割ることによりアルコール度数を和らげてくれます。
また、水分を摂ることで、アルコールによる利尿作用を促進してくれます。
休肝日を設定する
体に入ったアルコールは、睡眠中に肝臓で分解されますが、毎日飲むことで肝臓への負担がかかってしまい、飲み過ぎが重なると、肝機能障害を招くリスクがあります。
このため、週に2日は休肝日を設けながら、うまくお酒の量をコントロールしていくと良いでしょう。
まとめ
本記事では、体に悪いお酒の種類をピックアップしながら、その特徴を解説してきました。
お酒は、時に健康に良く、時に健康に悪影響を与える飲み物です。
アルコール度数や糖質など、お酒の種類によってはその値は様々ですが、相対的に適量を嗜むことにより、体への負担を軽減させることが重要であるといえるでしょう。
本記事のランキングでは、必ずしも体に悪いお酒を位置付けることには重きを置かず、それぞれのお酒の持つ特徴を解説しています。
これを参考に、上手にお酒と付き合いながら、健康を意識した飲み方を探ってみてはいかがでしょうか。